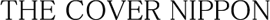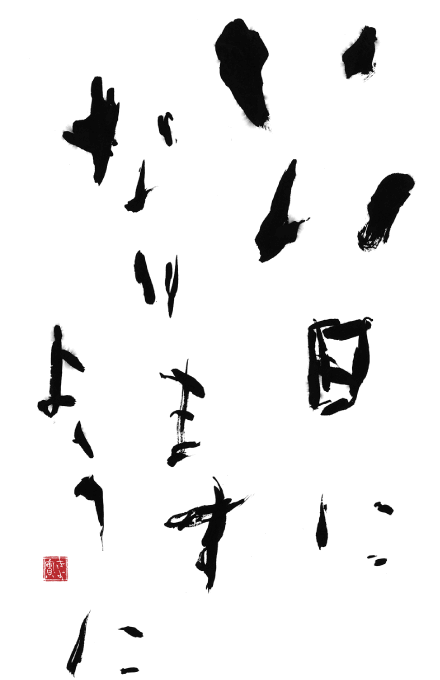和食器の愉しみ
和食器を上手に暮らしに取り入れてみたいけど、種類も多く、お手入れ方法や何から揃えていいのかわからない。と思っている方も多いはず。たしかに和食器は洋食器と比べ、器の素材、色柄や形など多種多様で、それらを季節や料理にあわせ、様々に組み合わせて使います。昔ながらの伝統技法や熟練した職人の技術でつくられた和食器は、かたち・絵柄などどれをとっても、日本各地の風土から生まれた技術や、季節を大切にする暮らしのスタイル、日本の美意識までも再認識させてくれるものばかりです。
そこでTHE COVER NIPPONでは、そんな日本の財産である、日本で育まれ丁寧につくられた「和食器」の数々より、ひとつづつ特集し、改めて「和食器の愉しみ」をお伝えしていきます。
第一回目は、有田焼を代表する窯元のひとつ、「源右衛門窯(げんえもんがま)」をご紹介します。
有田焼×越前漆器のコラボ、はじめに揃える和食器『くるむ』
最初に特集するのは、THE COVER NIPPONより生まれた、「源右衛門窯」とモダンな漆器にチャレンジし続ける越前漆器「土直漆器」のコラボ、はじめに揃える和食器『くるむ』です。木目が美しい欅(けやき)と漆のもつ自然で豊かな表情の”椀”と、愛らしい源右衛門窯を代表する梅地紋の”碗”、毎日つかう”椀と碗”をつくりました。
和食器は手で持っていただきます。『くるむ』は、毎日食卓を囲む幸せを、両手のひらでやさしくくるみ、感じていただけるように、と、手で持つことを意識した、やさしい丸みをおびたかたちにしました。また、様々なかたちが多く仕舞いにくいと敬遠しがちな和食器も、現代の暮らしにあわせて収納場所を取らないよう、重ねて収納できる”組み椀/碗”にし、色柄も、今のスタイルにあわせ、和洋のどんな料理にも馴染むような色合わせです。
最初の一歩、こんなあたたかな和食器からスタートしませんか。

源右衛門窯 取り皿コレクション
和食器好きの方が真っ先に思い浮かべるのは、色柄や形が様々あるうつわを、お好みで組み合わせる楽しさではないでしょうか。微細な染付からおおらかな絵付けまである源右衛門のうつわは、まさにその醍醐味を楽しめます。手のひらに乗る小さな手塩皿から、お料理を取り分ける取り皿まで様々な絵柄や形、大きさの取り皿を、THE COVER NIPPONセレクションで取り揃えました。お取り皿がいろいろ揃うと、食卓が華やかになり、組み合わせによってもいろいろ楽しめます。
今回は特別に、普段はセットでしか販売していないものも一枚づつお買い求めいただけ、またTHE COVER NIPPONセレクションのギフトセットもご用意致しました。和食器をついつい集めたくなること間違いなし。
これから深まる秋の食卓をうつわとともに愉しみましょう。

源右衛門窯 とは
宝暦三年(1753)創業と伝わる源右衛門窯が、現在の地に築窯したのは明治初年の頃。古伊万里の伝統技法を継承する民窯として、その歴史を積み重ねてきました。明治から昭和初期にかけては、おもに高級料亭向けに会席料理の器を手がけ、日本の食文化が多彩で豊かになった昭和30年代からは、家庭用の食器作りに力を注いできました。その流れは途絶えることなく今日に至り、食卓を彩る器制作に取り組みながら、多様化する現代のライフスタイルに向けて、磁器の持つ新たな可能性を日々発信しています。