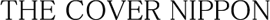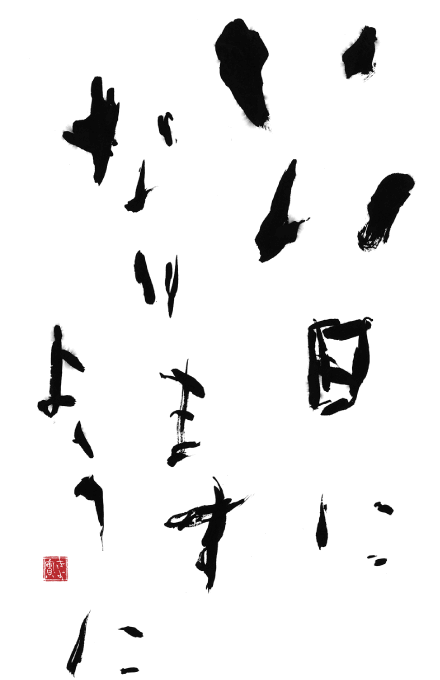梅雨の一日、有田焼を代表する窯元のひとつ、源右衛門窯 (げんえもん)を訪問。歴史ある源右衛門の数々のコレクションの数々やそれらを生み出している工房を金子社長自ら、ひとつひとつ丁寧に説明してくださった。
源右衛門窯は、緻密な中に勢いのある絵付けを得意としている窯元で、古伊万里の伝統技術を受け継いでいる。職人が作業している工房を一般公開している数少ない窯元で、見学のために開放された工房でなく、実際に出荷される商品を作っている工房を一般公開している。歴史ある窯元らしく、古い木造の佇まいをそのまま残しており、綺麗に整頓されている工房。そこに感じる職人の空気は独特の世界観が有り、それを生業としている人達の強いこだわりや気遣いが随所に感じられた。

そんな中、とても印象的だったのは、それぞれの工程に、職人が細部までこだわって作業していること。また職人の技術だけではなくその工程の専門性と連携の凄さ。
そもそも、自分の仕事として考えてみると、ある一つの作業だけをひたすら根気強く一日続けること、そしてそうした細やかな作業を生涯の仕事とするということ。それ自体がすでに自分の想像を遥かに超えている。しかし、そうした日々の積み重ねと修練による年月の中で職人は個人の個性ではなく窯元の個性というものへと変化していくのだ、と改めて感じることができた。
たとえば、加飾につい目がいってしまいがちだが、生地の段階から、仕上がりの美しさや使用する際の口当たりなど、皿の裏、カップの取っ手の付け根、など一見気付かないような、細やかなところにも人の眼と手を介していた。また、常識で言えば型で成形するものも手作りで、寸法は均一に成形しているが一つ一つ味わいがあり、目で見ただけではわからないが、うつわを手にしてみると感じる。やはり人は五感で感じることを実感した瞬間だった。

また、絵付けでは、ダミの量が多く白磁本来の白さを際立たせダミ自体にも部分部分で濃さを変えていることで源右衛門独自の器になっていた。一つの商品が完成に至るまでに何人もの職人の手を介在している。これだけ多くの手を通って完成しているのに、どれも違わず均一の美しさを保っている。普段私達が見る完成品というのは、改めて考えてみると驚異的なまでに均一な仕上がりで、本来この均一さができる人こそが職人だと工房見学の中で教えられた。
呉須や筆、気温湿度によっても色の濃さが変わってしまうため各職人に持ち味があり、窯元の方々は器を見るだけで誰が描いたか分かるという。また、職人のこだわりや個性は、使っている道具にも現れていた。作業で使う机や畳座も職人それぞれがカスタマイズして自分好みの高さや仕様にしているのだという。道具への愛着や人柄が垣間見れるのも工房見学ならではの醍醐味だ。

昔使われていた窯を見せてもらった。中に入ると内側のレンガには高温で器を焼く際に飛んだ灰等がガラス状になっておりテカテカとタイルの様な状態である。有田の街で見かける「とんバイ塀」はまさにこの古い窯の壁を使用しているとのこと。窯のそばに 牙のような三角錐の不思議な形の物が置いてあった。これは温度計の様な役割をするという。窯の中に入っている焼き物と同じ成分で出来ており窯の中の温度が高くなるにつれ柔らかくなり重力で曲がる。職人が窯の温度を確かめる為に必ず必要なものだったそうだ。

「古典文様を引用しながらも、先代はそれを自分のフィルターにかけて、現代の市場に合うようにアレンジしました。そのアレンジ力が優れていたのだと思います。」と 金子社長。その話を聞くにつれ、源右衛門窯の手描きの柄のデザイン性や味わい、絵付けひとつひとつに意味があり、そうしたことひとつひとつが、永いあいだ、源右衛門窯が人々を魅了し続けている所以だろう。