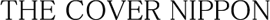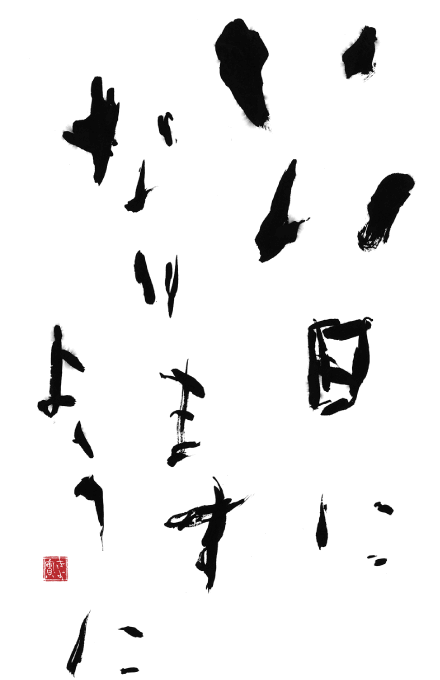「少しの回り道とモノづくりへの変わらない思い」
江戸切子(東京)vol.2
夏至を迎え、これから夏の盛りへと、暑さが日に日に増していきます。先月に引き続き、企画展「不易流行」にて江戸切子を特集しています。繊細なカットが光をまとい、ひんやりとした感触はひとときの涼を運んでくれます。
今回、江戸切子の煌めきが生まれる場所を訪ね、モノづくりに取り組む人々の想いに触れてきました。インタビューの第2回は、江戸川区松島に構える大場硝子加工所。社長で、伝統工芸士の大場和十志さんにお話を聞きました。一度は一般企業に就職し、25 歳の時に父親に師事するかたちで切子職人への道を歩み始めた大場さん。「つくる」をつないだ先に見えたものとは?
INTERVIEW
江戸切子 伝統工芸士大場 和十志(大場硝子加工所)
縁の下の力持ちに価値を感じて
正直言って、学生のころは家業(硝子加工)にさほど興味はありませんでした。高校時代は放送部に所属。文化祭は毎年大掛かりなステージが評判で、私たちはプロユースの機材を借りて、ミキシングを担当していました。演奏者の音をいかにいい音で観客に届けるか。会場を後にする観客が「すごかった」「良かった」と話しているのを聞いてとてもうれしく、縁の下の力持ちという存在に価値を感じました。今考えれば、これもモノづくりのひとつですよね。とはいえ、学校を卒業して就職したのは、自分とは縁遠いアパレルの世界。営業職に就き、すぐに退職したのは自分の考えの甘さとしか説明しようがないです。そのとき私の心にあったのは、モノづくりへの意欲。そして、ふと横を見ると正真正銘のモノづくりがあったわけです。灯台下暗しですよね。それで25 歳の時に父に頼んで、父に師事するかたちでこれまでやってきました。父の気持ちはどうでしょうね。喜んだ反面、お荷物が増えたといった感じでしょうか(笑)。
父の代は問屋さんやメーカーさんからの加工委託が主体で、自分の色を出してはいけないという事業所でした。ですから、これまでほとんど大場硝子加工所の特長を意識したことはありません。企業形態としては良くないことかもしれませんが、ただ、できる限り丁寧なモノづくりをやっている自負はあります。それは、妥協しないということではなくて、お客様に喜ばれるようなものをつくり続けるということ。私の代になって、加工委託はしつつも、自社の商品をつくり始めましたので、今は大場硝子加工所の製品イコール私の作品です。修行に入っている者もいて、そうした人がこの先増えれば、自ずと変わっていくだろうし、また変わっていかなければならないんだろうとも思います。
盛り上がる江戸切子のもうひとつの背景
そもそも、今では色被(き)せガラスのイメージが強い江戸切子ですが、それだけではありません。ホテルなどで使われるグラスに入った切子も自分たちの仕事です。つまり、工業生産的要素の強い手工業が減って、今は工芸的なものしか残らなくなってしまっています。ですから、江戸切子は確かに盛り上がっていますが、一方で工場の閉鎖も続いています。例えば、昔はシャンプーの容器も硝子でした。そういうものが昭和 30 年頃から次第になくなってきたことも、江戸切子のもうひとつの背景です。
伝統の伝承していくという使命
おかげさまで現在は百貨店の期間催事などで、お客様の声をダイレクトに聞かせていただいています。水飲みグラスでも何でも、気が付くと何となく手に取って使っている、私がつくったものがそんなふうに使われているのが一番うれしいですね。特別なものではなくて、空気のような存在。そこにあって当たり前で、なくなると寂しいと感じるもの。それなりのお値段がしてしまうので、なかなか難しいとも思いますが、それでも日常に溶け込むものをつくっていきたいと思います。
伝統工芸士の認定は、自分の今までしてきたことを認めていただいたと受け取っています。ですから、伝統工芸士になってもこれまでと変わらず、確実にモノづくりを続けていくだけです。続けていくということは、自分が受け取ったバトンを次の人に渡すということでもありますね。何かのテレビ番組で、「伝統は一つの革新から始まる」と話されていたのですが、本当にそのとおりで、伝統は最初から伝統ではありません。新しいものができて、それを見たみんなが「すごい」と思って取り入れて、そこに自分の想いを加えて、それが次の世代に伝わって、永遠とつながっていく。それが伝統になる。伝統というよりは、伝承と言えますね。
4年目になる弟子の女性はもともと大阪の子で、「職人を雇っていませんか」と電話をかけてきたのがきっかけでした。大抵はみんなそうやって自らこの世界に飛び込んできます。職人を募集するキャパのあるところは少ないですから。残念ながら、彼女の前に入ってきた 3 人は志半ばで挫折してしまったので、彼女には続けていってほしい。職人=男性・仕事 というイメージもあると思いますが、今の時代は男性も女性も関係ありません。
また、これから先は自分専用の型を展開していくことが求められてくると思います。一点ものであれば素材をつくる硝子作家さんとのコラボレーションするのも一つの手でしょう。ただ、職人と作家さんって意外と接点がないんです。また、切子に耐えられる素材をつくってもらえるかどうかという問題もあります。さまざまな人とディスカッションして、 江戸切子の未来をつないでいきたいと思います。
EVENT
出展者プロフィール(大場硝子加工所)
 大場 和十志
大場 和十志
1970 年東京都に生まれる。1995 年大場硝子加工所入社、父・十志男に師事し、2006 年に代表就任。2010
年日本の伝統工芸士(江戸切子)に認定される。第 22 回江戸切子新作展で東京都産業労働局長賞を受賞。
2011 年経済産業省主催 WAO 工芸ルネッサンス・プロジェクトに入選。