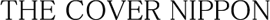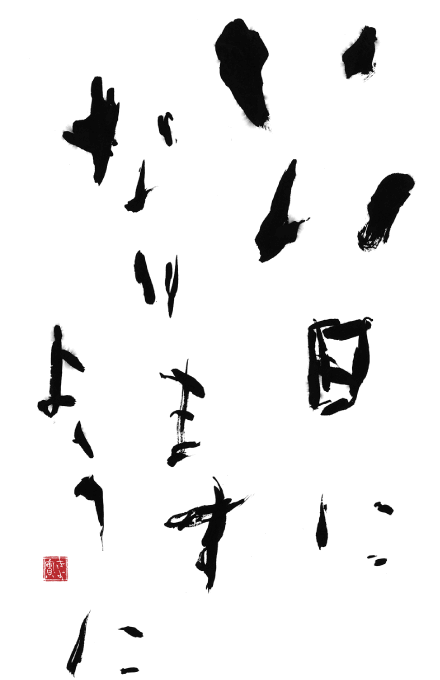古くは瑠璃(るり)と呼ばれ、シルクロードを通り日本に伝わったガラス。正倉院の「白瑠璃碗」もそうした舶来ガラスの一つです。今回の不易流行では、繊細な輝きで人を魅了する日本の工芸ガラスの代表格「江戸切子」を特集し、江戸時代の面影や「粋」の精神を内包しながら進化を続ける工房の若手たちにも注目。職人のこだわりとともに江戸切子の今をご覧いただきます。

西欧から渡来したガラスへの憧れ
日本のガラス製造の歴史を紐解くと、時は江戸時代中頃、中国から長崎に伝わった吹きガラス「ビイドロ(ポルトガル語でガラスの意)」が庶民にも広まり、江戸時代の終わりにカットを施したガラス「ギヤマン(オランダ語でダイヤモンドの意)」が西洋からもたらされたことに始まります。
江戸切子は大名の庇護のもとに育った工芸ではありません。天保5年、江戸大伝馬町でびいどろ屋を営む加賀屋久兵衛が、この舶来の「ギヤマン」を手本に木の棒と砂で試行錯誤しながらカットガラスの製作を始めたのがはじまり。江戸の人々の好みとも合致したことで暮らしの器として庶民に愛され、発達し、ペリー来航時には江戸切子が献上され、その美しさに驚いたという逸話が残っています。

江戸の粋
赤や青がとても印象的な江戸切子ですが、昔は透明のガラス(透きガラス)にカットが施されていました。昔のガラスは大変もろく壊れやすい、とても儚(はかな)いものでした。ゆえに、美人をその儚さ・美しさを例えて「ビイドロ」「ギヤマン」と呼んだそうです。
もろく儚いガラス、職人が施しす美しいカット、キラキラとまばゆい光を放つ「江戸切子」は、まさに「江戸の粋」に通ずる美意識そのものでした。
成熟した町人文化から生まれた江戸切子には、10種類もの代表的なカットパターンがあり、当時の趣を今に伝えています。
もともと舶来品だったカットガラスですから、代表的な模様「霰文(あられもん)」「魚子文(ななこもん)」も、日本独自のデザインというわけではなく、ガラスの魅力を十分に発揮するこのシンプルなデザインが当時のイギリスあたりで数多く作られ、それらがちょうど江戸好みの模様であり、日本独特の模様への想いが追加され、江戸切子独自のカットグラスの世界が繰り広げられることとなりました。
透明感が涼やかで、放つ煌めきが食卓を華やかにしてくれる江戸切子は、ある人にとっては、夏の定番だったり、日本料理に彩りを添えたり、レトロで浪漫あふれる食卓を演出してくれる、すでに愛着のあるアイテムに違いありません。
模様も用途も庶民の暮らしと共に発展し続ける江戸切子は、夜景のようにキラキラと光り輝くカットの妙やカジュアルで若々しいデザインが生み出されるなど、ただ懐かしいだけでなく、時代とともにあり続ける工芸品でもあります。