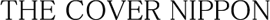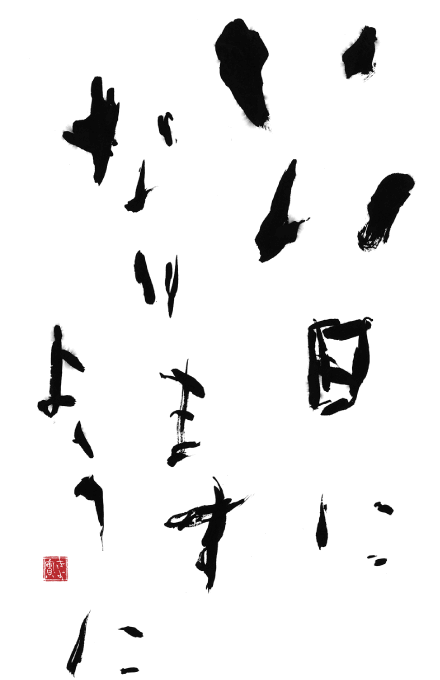骨董のある風景 菊見月 重陽の節句Japanese Antiques -Enjoy chrysanthemums-
五節句の最後を飾る重陽は、菊の節句です。縁起がよいとされた陽数の極みである「九」が重なった九月九日は、菊を愛でて菊でもてなす日。9月は大人の節句として存分に菊を楽しみましょう。
September 9th is the day to admire and entertain with chrysanthemums when the nines which are the extremes of the positives numbers overlap. Let's fully enjoy September with chrysanthemums.
大人たちの節句
五節句の最後を飾る重陽は、菊の節句です。 五節句の風習は、もともと中国から伝わり奈良時代に朝廷の行事になりました。 縁起がよいとされた陽数(奇数)の極みである「九」が重なった九月九日が重陽の節句です。 この日は「菊」が景物となります。菊を愛でて菊でもてなす日です。

春から桃の節句、端午の節句、七夕と、現代ではやや子ども向けといった印象の行事が続きますが、重陽の節句には、大人が楽しめるしっとりとした雰囲気があるように感じます。
黒塗の漆器の質感のきめ細やかさに、黄色い菊が舞うと、はっとした美しさに息を飲みます。 肌は残暑を感じていても、目から一気に季節を感じさせる、素晴らしいコントラストです。
サラダやお吸い物、お酒にそのまま散らすと簡単で綺麗です。 またいつもは残すお刺身のつまの菊も、この季節だけはお醤油皿に散らしてお刺身を召し上がってみてください。他のつまやけん同様、菊にも毒消しの作用もあるのです。

菊は骨董でもよく見るモチーフです。 「九」と「久」が同じ音であることから、九月の花である菊は、幾久しく長寿をもたらすとする吉祥紋です。また黄色や紫色などの菊の花の色は、高貴なる身分の人が身につける色であり、尊厳や権限などの最高のイメージと重なります。鎌倉時代の後鳥羽上皇は特にこの花を好み、持ち物すべてに菊の模様をつけたと言われています。以来、天皇を象徴する文様になりました。 菊の蒔絵に絵付け、また菊を型どったお皿など、9月は大人の節句として存分に菊を楽しみましょう。
文/写真:藤川佳惠
*歴史の解釈には諸説ありますので、あくまでも一説とお考えください。