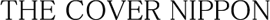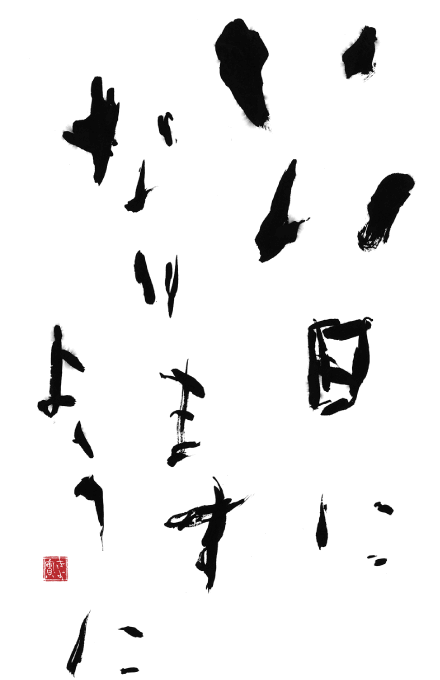幕末の激動が生んだ究極の切子
江戸時代、薩摩藩島津家27代当主・島津斉興が、製薬工場を設立しそこで必要な医薬品用のガラス器をつくるため、江戸から職人を招いたことからと始まりました。その後ペリー開港の2年前、篤姫の養父であった島津家28代当主・島津斉彬が薩摩切子を開発し、将軍家の献上品や海外交易品とされ、大胆なカットや細かい文様から生まれるグラデーション「ぼかし」は、どこか幽玄な味わいを醸し出し、当時諸外国を魅了したと言われています。ところが斉彬の急逝や薩英戦争による工場の破壊され、維新の動乱の中、衰退の一途をたどり、わずか20年足らずで薩摩切子は終焉してしまいます。
120年の沈黙を破り復活した黒切子
そして100年後の1985年、薩摩切子は、島津家の主導で復刻が試みられ、なかでも黒切子は十数年かけて開発されました。薩摩切子の生地は透明ガラスに色ガラスを厚く被せた「色被せ(いろきせ)」という技法で作られます。収縮の度合いが異なる2色のガラスの膨張を揃えながら吹くことは通常でも難しい上に、生地の裏側が見えないので手に伝わる感覚と微妙な音の揺れだけを頼りに繊細な模様を削る黒切子は、まさに五感が生み出す卓越した手技、究極の切子と言えるでしょう。
彗星のように現れて消えた薩摩切子は、色褪せることなく、今も人々をひきつけてやみません。