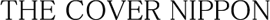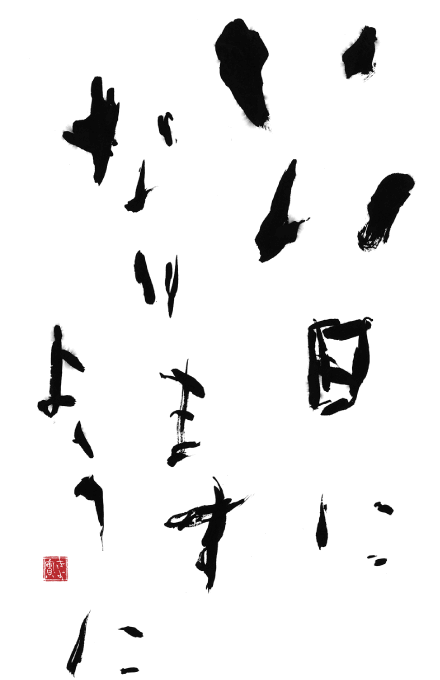7月7日は七夕。きめ細やかな星の群れ天の川が夜空にかかります。空から降ってくるほどの満天の星は、どこか線香花火に似ています。夏の風物詩、日本の美の代表格とも言える花火の中でも、線香花火はその儚さから、日本人の心を掴んでやみません。
江戸の夏の風物詩
日本人で初めて花火を鑑賞した人物は、慶長18年(1612年)8月6日に駿府城から花火の打ち上げを見た徳川家康と言われています。それ以降、国内での製造も始まり、花火は新し物好きの江戸っ子の間で瞬く間に広がり、三度の花火禁止令が発令されるほどの人気となりました。
線香花火が初めて歴史書に登場したのは1608年。江戸前期の俳諧集「洛陽集」に、花火を香炉に立てて遊んでいる女性の様が詠まれており、香炉や火鉢に立てた花火の格好が仏壇に供えた線香に似ているところから「線香花火」の名前がついたと言われています。つくり手である産地と職人、売り手である商人、そして夏の風物詩として花火を愛する市井の人々によって、日本の花火、そして線香花火は、江戸文化の象徴として確立され、我々が生きる現代に至るまで400年間、脈々と受け継がれてきました。
純国産線香花火の復活
400年に渡って日本の夏の風物詩として愛されてきた線香花火ですが、実は1998年に国産が絶滅してしまいます。昭和50年代に入ると、安価な中国産の線香花火が大量に流入。その圧倒的な価格差により、徐々に国内の産地への打撃が大きくなっていきます。そして、まずはじめに昭和60年(1985年)に信州の線香花火製造する全店が廃業に追い込まれ、続いて平成8年(1996年)には三河地方の全店が廃業。さらに平成10年(1998年)、九州の最後の一店が廃業し、国産線香花火は絶滅。産地が途絶えたことから、つくり手である職人がいなくなってしまい、長い歴史を持つ技術も途絶え、400年の歴史に幕が降ろされました。
そんな状況の中立ち上がったのが、商人の町としても知られる東京の下町蔵前の「山縣商店」でした。山縣商店は、大正3年創業の100年以上続く老舗花火問屋。日本の線香花火の伝統を守らなければいけない。江戸文化に対して特に熱い思いを持つ五代目山縣常浩が中心となり、三河地方をはじめとした産地や職人を訪ね歩き、日本の伝統、線香花火への想いを伝えていきました。そして、和紙、染料、火薬、製法のすべてを、昔ながらの伝統的なつくり方で復活させることに、メーカーや職人、産地問屋と手を携えて取り組み、2,000年(平成12年)、2年以上の歳月をかけついに純国産線香花火が復活しました。それがこの、「大江戸牡丹」です。

丁寧に一本一本縒りあげられた職人の手仕事
この線香花火「大江戸牡丹」は、愛知県(三河地方)でつくられています。国内の花火の産地として有名なのが、三河、福岡、信州、いずれも強い戦国武将がいた地域です。武器として火薬を多く保有していたことから、花火の生産も活発となり、線香花火の産地としても栄えました。三河地方は、線香花火だけでなく、玩具花火も含めて国内の花火の一大産地で、古くから続く花火メーカーが多数在ります。
日本の線香花火は、手しごとで作られています。ものづくりの現場では、安全上の理由から電灯や暖房など使わないため、製造時間は日照時間に左右され、夏は暑く冬は寒い中で、この道数十年の熟練の花火職人が、ひとつひとつ丁寧に心を込めて火薬を調合し、カラフルに手染めした和紙で火薬を包み、そして1本1本縒っていきます。火薬の粒を肌で感じながら丹念に調合して、天然染料で染めた和紙で包んで撚ってゆきます。この丁寧なしごとによって火薬が紙の繊維の中に入り、火をつけたときに美しい火花を散らすのです。
長い年月、花火を手づくりしてきた職人たちの手には年輪が刻まれ、ものづくりの職人独特の、強くてやさしい、そして美しい表情をしています。そんな職人達が丹精込めて、1本1本大切につくる「大江戸牡丹」。江戸の昔から続く日本の伝統美がここにあります。