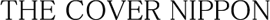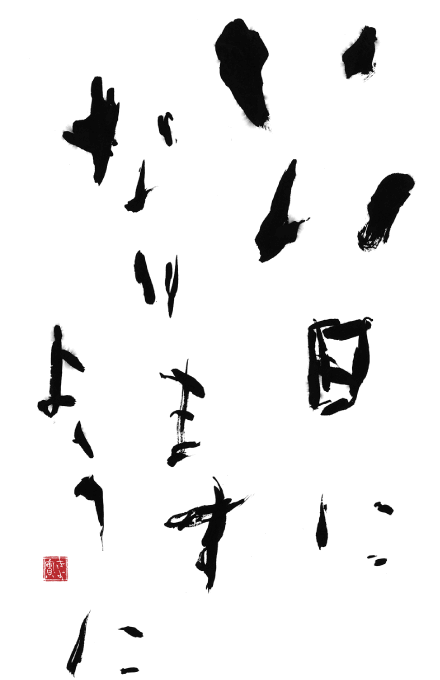?昨年に引き続き 今年も JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2015 に参加します。今年は高山茶筌(奈良県)とコラボレーションします。
※期間中は 実演(11月1・2日)など様々なイベントをご用意しています。店頭までぜひいらしてください。
一子相伝の技が生む芸術美 茶人が愛する高山茶筌
室町時代より職人の手仕事により生み出されてきた高山茶筌。その素材や形は茶道の流派や点前によって異なります。このイベントに合せ、約30種類の茶筌を新たに製作、展示販売致します。茶道具だけに収まらない、造形美の茶筌をお愉しみ下さい。

高山茶筌について
茶道の創始者でもある村田珠光の依頼によって作ったものが始まりです。
以後、その製法は城主一族の秘伝とされ、代々後継ぎのみに「一子相伝」の技として伝えていましたが、後になってその秘伝は、主だった16名の家来に伝えられることとなり、今日まで脈々と伝えられ、現在では奈良県の高山が全国で唯一の茶筌の産地になりました。
また高山茶筌は120種類もあり、茶道の流派と、薄茶用、濃茶用、献茶用、野点(のだて)用、茶箱用等の用途によって、素材や形、穂の数等が異なります。また、茶筌の味削りという工程のでき具合により、お茶の味が微妙に異なります。
高山茶筌について詳しくはこちらからご覧いただけます。
茶筌の製作実演
開催日時 11月1日(日)13:00~18:00 / 11月2日(月)11:00~16:00
会期中の2日間、高山茶筌の産地より、職人の方が来店し、実際の細やかな手仕事を、すぐそばでご覧いただけます。是非この機会にお越しください。
<繊細で優美な手仕事>
高山茶筌はすべて職人の極めて繊細な手仕事から生まれています。製作に使う道具は小刀とやすりのみ。機械には一切頼らず、一つ一つ丹念に作られています。茶筌は8つの工程を経て一本が完成します。1つの技を習得するのに必要な歳月は2年と言われ、1人の職人が一人前になるまでには最低でも16年は修行を重ねなければなりません。1mmに割った竹をさらに0.4mmと0.6mmに割っていく繊細な工程もあり、人の手だからこそ、こうして優美な茶筌が生まれるのです。
関連リンク
JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2015奈良県高山茶筌共同組合