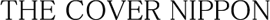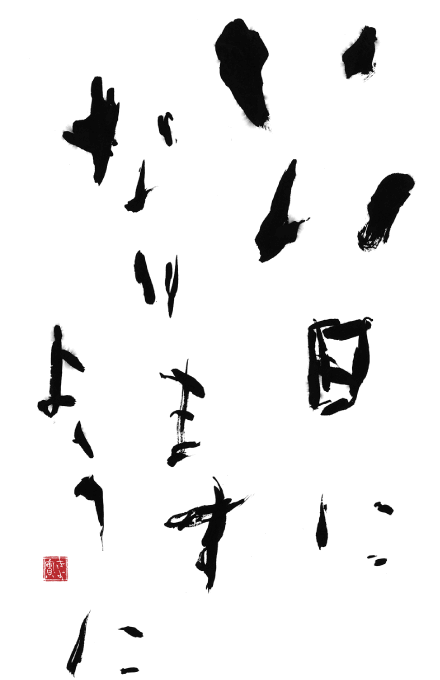「美濃焼」
 「美濃焼」とは岐阜県美濃地方の東部、東濃地方といわれる多治見市・土岐市・瑞浪市・笠原町で生産されるやきものの総称をいいます。質の良い土に恵まれ、平安時代から美濃焼の生産で栄え、美濃焼の集散地として発展してきた陶磁器産業の中心地でした。
「美濃焼」とは岐阜県美濃地方の東部、東濃地方といわれる多治見市・土岐市・瑞浪市・笠原町で生産されるやきものの総称をいいます。質の良い土に恵まれ、平安時代から美濃焼の生産で栄え、美濃焼の集散地として発展してきた陶磁器産業の中心地でした。
桃山時代には京から訪れた陶工や茶人との交流が美濃焼をより洗練させ、志野焼や織部焼をはじめとする美濃焼の名は全国に知られるようになります。その後、幕末に九州有田から磁器の製法が伝えられると、磁器原料に恵まれた風土を活かし、生産の中心はかつての陶器から磁器へ。明治時代に入ると、国内の需要が増えたことと輸出が盛んになったことに加え、陶磁器産業の近代化とともに生産量は飛躍的に拡大しました。昭和期には、人間国宝・荒川豊蔵氏による志野焼の復活をきっかけに美濃古陶が再び焼かれるようになり、最近では若い陶工達が増え、陶器の生産も多くなっています。

わたしたちのまわりには、さまざまなやきものがあります。毎日生活で使う食器をはじめ花瓶や置物などの装飾品、内外装用タイルなどの建築資材という従来のやきものから、IC基盤などの電子部品、新しい産業分野の航空宇宙産業においてもファインセラミック製品が使われ必要とされています。
美濃焼では、こうしたやきものを長い歴史と伝統に支えられ生産しております。 現在、東濃3市(多治見市、土岐市、瑞浪市)の陶器と磁器を合わせた生産量は、食器類が約60%、タイルは約48%を占めています(平成22年現在)。美濃焼では、こうしたやきものを長い歴史と伝統に支えられ生産しております。 日本のやきものの代表といっても過言ではありません。日常生活の中で何気なく使われ、知らないうちに暮らしの中にとけこんでいるやきもの、それが美濃焼です。